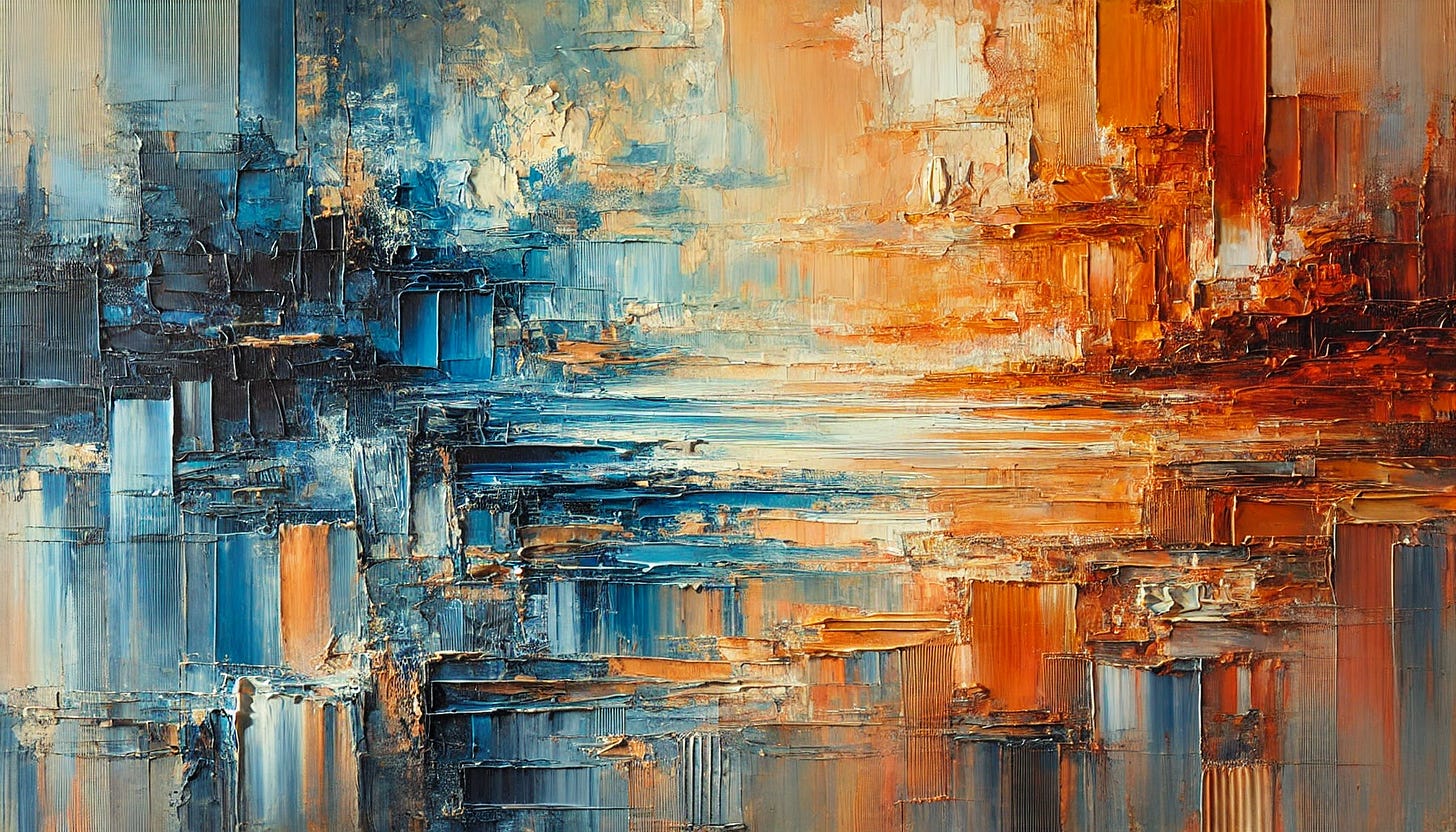穏やかヤンキー、都市メガネ
リモートワークの火を絶やさないで
マイルドヤンキーという言葉を久しぶりに聞いた。
🖇️ マイルドヤンキー層が根付くところに暮らすと日本の土台を支えているのはこの層だと痛感するしこの層が広がることで幸福が広がるのではないかとさえ思う - Togetter [トゥギャッター]
マイルドヤンキーとはざっくり言うと「地元志向が強く仲間や家族を大切にし、車や実用的なブランドを好むライフスタイルや価値観を持つ、地方や郊外に多い若年層」を指す、2014年に初出のマーケティング用語1。
ちょうどその頃「ヤサイも果物も美味しい某政令都市の駅前に建造される巨大ショッピングモール内に作るクリエイティブスペースのコンセプトワーク」に携わっていた僕は「トーキョーでITをやっているホワイトワーカーの視界に入らない日本のマジョリティ像」としてマイルドヤンキーを理解しようと努めていたことを思い出した。
それから12年。上記のXまとめでは、塾講師が地方でのマイルドヤンキー的な親御さんたちを見て、彼らこそが日本を支える幸せな層ではないか、都会の競争社会で疲弊している人たちよりも幸福度が高いのではないか、というつぶやきで一石を投じ、それに対しまたネット民がやいのやいの言っている。
ところで、「ヤンキー」という言葉のチョイスにどうしても、悪意、とまではいかないけど、都会のホワイトカラーが地方の善良な生活者をステレオタイプ化して見下す意識が感じられてしまい、ネットの燃料になりがちだ。
じゃあそうやっていつもネット越しに石を投げている「都会のホワイトカラー」さんたちにも愛称をつけてあげたらいいのでは?
と思いたってAIにマイルドヤンキーの対義語を尋ねてみたところ、出典n=1の「スパイシーメガネ」という言葉をXから拾ってきた。
う〜ん。スパイシーはよくわからないけどメガネはよさそうだ。
「メガネ」と言われたときのイラッとくる度は「ヤンキー」といい勝負かもしれない。
・・・ということで、マイルドヤンキーの対義語として「アーバンメガネ」とかいかがでしょう?
閑話休題。
自分はもちろんアーバンメガネだ。高校卒業後すぐに田舎を出て京都の大学に進学して卒業後は東京でIT企業に就職。何度も転職を経験しながらもホワイトカラーは変わらず今はMacBookを使って複数の仕事をしている。結婚はしているが子供はいなくて賃貸暮らし。自家用車は持たなくてもタイムズカーで十分。交友関係は、大学進学後もしくは仕事を通じて都会で出会った人がほとんど。まさに、マイルドヤンキーとは真逆の人生を歩んできていると言える。
・・・のだが、実は自分にとって10年前にはリサーチ対象でしかなかったマイルドヤンキーが、少しずつ変化している。
友人のヤサイ畑を手伝ったり、人混みを避けて道の駅巡りをしながらその土地の文化を面白がったり、毎日の自炊が楽しくなって広いキッチンが欲しくなったり、という価値観の変化を経ていつの間にか、「マイルドヤンキー」的な暮らしを求めている自分がいる。マイルドヤンキーの言葉の指す意味は特に変わっていないのに。どこへ行っても代わり映えのしないロードサイドのチェーン店?刺激的な文化資本がない?まあそういうのはたまに都会に顔を出して摂取すればいいんじゃないの。
そう思えるようになったのは年を取ったからだけではないと言いたい。
そう、2014年にはなかった「リモートワーク」が僕らにはある。都会のIT会社に勤めていても都会のオフィスに毎日出勤しなくてよくなった。都会に住むことにこだわらない人は、完全リモートワークができる会社に勤めることで都会に住まなくてもいい、という選択肢もできつつある。
なんと素晴らしい世の中に向かっているのだろう。
一方でそんな脱アーバンメガネ勢の不気味な脅威となっているのが企業のRTO(リターン・トゥ・オフィス)トレンド。
🖇️ LINEヤフー「フルリモート廃止」は当然といえる訳 - ライブドアニュース
コロナ禍の中で声高にフルリモートを謳っていた大手IT企業がそれを撤回し、社員に出社を義務付ける方針に戻す発表したことは大きな議論を呼んでいる。
会社の言い分は大きく2つくらいありそうだ。
ひとつ目は表の理由で「競争力の低下」。
これは経営陣が見たいものだけを原因にしているに過ぎないと言いたい。
コロナ禍以前は出社が当たり前で競争力があったが、リモートワークを導入した後に競争力が低下したため、リモートワークだけが原因だと決めつけている。
未来側から指摘するならば、リモートワークに対応できなかったこと、リモートワークという変化で競合よりレバレッジを効かせられなかったことがまずかったのだ。会社に社員を集めて拘束するという荒治療では一時的にパフォーマンスが向上するかもしれないが長続きしないだろう。
長い目で見れば、従業員の生活を犠牲にしてまで都会に縛り付けるよりも、それぞれの生き方を尊重して過干渉せず、幸せに暮らしてもらえるようにすることが、同じ仲間と成長しながら長く続けられるんじゃないだろうか。傭兵集団ではなく会社としてやるのだったら。
ふたつ目は(大きな声では決して言わないけど)「忠誠心の可視化」。
従業員がかつては会社に捧げていた余剰時間を、家族や地域活動、副業などに時間を使うことを快く思わない経営層がいる。
会社というコミュニティの手触りが少なくなったことが気に食わないと感じて、会社への関与時間で忠誠度を測ろうとしているマネージメント層がいる。
大事なことは成果への関与に尽きるわけで、成果をあげている社員に時間や場所で忠誠心を求めないでほしい。もし、パフォーマンスが悪ければしかるべき指導や処置をすれば良いということだ。(その中に「出社」という「お仕置き」は嫌だがアリかもしれない)
オールドタイプなのさ。ちょっと前の痛みを忘れて、次のことをやる。2
どれだけ従業員の時間とか人生を会社に捧げてるかみたいなもので忠誠心を測るという会社があったらこれからは「それはそれは貴社はなんともユニークな経営方針をお持ちですね」といって差し上げたい。
機動戦士Zガンダム 第37話 「ダカールの日」アムロ・レイの台詞より